タグ
売買ローン
投稿日:2025/05/16
【5分でわかる】住宅ローン保証料!借入前に学ぶべき事を解説します
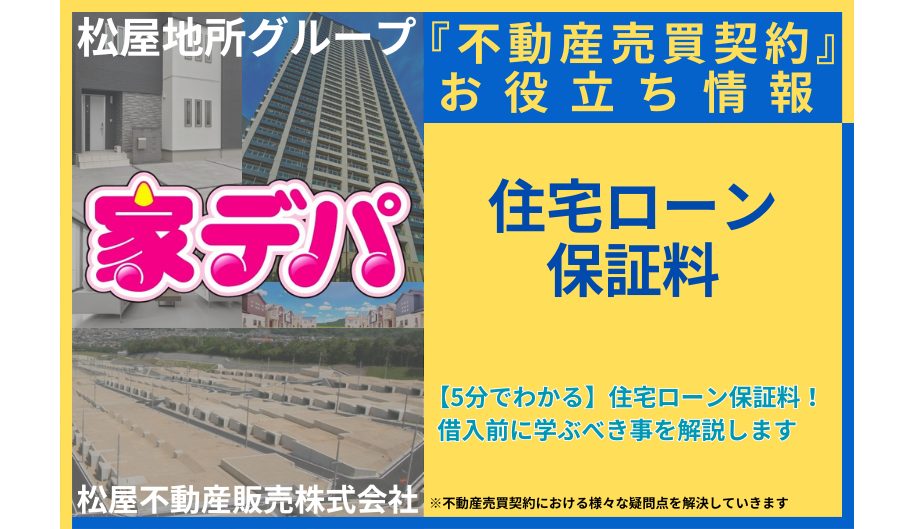
「住宅ローンの保証料って何?払わずに済む方法はある?」
「保証人との違いや外枠方式と内枠方式もチンプンカンプン…」
住宅ローンの保証料を理解せずに契約すると、外枠方式か内枠方式かで総支払額が数十万円変わることも。保証会社が代位弁済する仕組みや保証人との違いを押さえれば、自分に最適なプランが見えてきます。本記事では“5分でわかる”を合言葉に、初めての方でもステップ・バイ・ステップで節約術を学べるよう、支払い方式比較・返戻金シミュレーション・審査突破のコツまで網羅。読み終える頃には「どの保証料方式を選ぶべきか」「節約できる余地はどこか」がクリアになり、安心して借入手続きを進められるはずです。まずは手軽に読んで、将来の家計に“余裕”を作りましょう。隙間時間でサクっと知識を吸収して、金利上乗せ型の落とし穴も回避!
住宅ローンの保証とは?まずは超基本を3分で理解
住宅ローンを借りるときによく耳にする「保証」とは、万が一契約者がローンを返済できなくなった場合に備えて、保証会社が代わりに返済を肩代わりしてくれる仕組みです。簡単に言えば、昔は親族などに連帯保証人になってもらいましたが、現在は多くの金融機関において保証会社に保証料を支払い、保証人の代行を依頼するのが一般的です。この保証のおかげで金融機関は安心して融資できますが、契約者は契約時に「保証料」という費用を負担することになります。
保証会社を利用するといっても、契約者の返済義務がゼロになるわけではありません。保証会社が銀行に立替払い(代位弁済)した後、契約者は保証会社に対して立替分を返済していく義務が残ります。つまり保証料は、銀行のリスク軽減のための費用であり、契約者にとっての保険ではない点に注意しましょう。まずはこの基本を押さえた上で、次章以降で詳しく解説していきます。
なぜ保証料が必要なのか?金融機関・保証会社・契約者の関係図
図:住宅ローンにおける銀行・保証会社・契約者の関係(概略)

住宅ローンでは、銀行・保証会社・契約者の三者間で以下のような契約関係が成立します。契約者は銀行から融資を受け(図中右上)、同時に保証会社と「保証委託契約」を結んで保証料を支払います(図中左上)。銀行と保証会社の間では「保証契約」が結ばれ、保証会社は契約者が返済できない場合に銀行へ残債を立て替えることを約束します。
契約者が毎月、銀行にローン返済(図中右上)を続けている限り、保証会社が表に出ることはありません。しかし万一契約者の返済が滞ると(延滞や債務不履行)、保証会社が契約者に代わって銀行に残りのローン残高を一括返済します(これを「代位弁済」といいます)。代位弁済後、保証会社は契約者に対して立替えた分の返済を請求し(図中左上)、契約者は、今度は保証会社へ債務を返済していくことになります。要するに、保証料を支払って、保証会社を利用することで、銀行は貸し倒れリスクを回避し、契約者は身内の保証人を頼らずにローンを組めるメリットがあります。
では、なぜ金融機関はそこまでして保証を必要とするのでしょうか? 理由は銀行側のリスクヘッジにあります。住宅ローンは融資金額が大きく長期にわたるため、万一返済不能になると銀行の損失も大きくなります。保証会社が入ることで、銀行は抵当権による担保だけでなく保証会社からの回収ルートも確保でき、リスクが格段に下がります。そのため多くの銀行が保証料制度を採用しているのです。一方、契約者側も保証会社を利用すれば基本的に連帯保証人を用意する必要がなくなり、精神的な負担や人間関係のリスクを軽減できます(※ただし後述のケースでは連帯保証人が求められる場合もあります)。
まとめると、保証料は銀行・保証会社・契約者の三者それぞれにとって意味のある制度と言えます。銀行はリスクを減らし、契約者は保証人探しから解放され、保証会社は保証料収入を得る代わりにリスクを引き受ける――このような関係図になっているのです。
保証料の支払い方式を完全比較:外枠方式・内枠方式・事務手数料型
住宅ローンの保証料は、一律同じ支払い方ではありません。主に3つの支払い方式があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。ここでは以下の3タイプについて、仕組みと利点・欠点を丁寧に比較してみましょう。
- 外枠方式(前払い型) – 契約時に保証料を一括前払いする方法
- 内枠方式(後払い型) – 月々の金利に保証料分を上乗せして支払う方法
- 保証料ゼロ型(保証料ゼロ型) – 一見「保証料0円」に見えるが、実際は手数料に組み込まれる方法
外枠方式(前払い型)の仕組み
外枠方式とは、住宅ローン実行時に所定の保証料をまとめて支払う方式です。いわゆる「一括前払い型」とも呼ばれ、借入金額と返済期間に応じて保証料額が決まります。たとえば借入額が多く返済期間が長いほど保証料は高額になり、逆に短期間で返済するローンなら保証料率も低めになります。保証料率の相場は金融機関や保証会社によりますが、借入額の2.2%程度が目安です。一般的な35年ローンではほぼ上限に近い約2%前後となり、3,000万円の借入なら66万円程度を契約時に支払うイメージです。
外枠方式のメリット
外枠方式の最大のメリットは、トータルの支払額が最も少なくなる傾向がある点です。前述の通り一括で支払った保証料には利息がかからないため、長期的に見ると金利上乗せ型より総支出を抑えられるケースが多いのです。また、保証料を毎月の返済に組み込まないので月々の返済額を軽減できる利点もあります。さらに、後述する繰上返済時の扱いにも注目です。ローンを繰上返済や一括返済した場合、支払済み保証料の一部が「戻し保証料」として返金される仕組みがあり、結果的に支払った保証料のムダを取り戻せる可能性があります。例えば35年ローンを25年で完済すれば、残り10年分に相当する保証料が所定計算で払い戻されます(詳細は金融機関に要確認)。
外枠方式のデメリット
一方、外枠方式のデメリットは、契約時にまとまった現金が必要になることです。保証料は数十万円単位になるため、物件購入時の頭金や諸費用と合わせて準備しておかなければなりません。「住宅ローンを借りて資金調達するのに、また別途大金を用意するのは大変…」と感じる方もいるでしょう。特に購入諸費用をできるだけ抑えたい場合、前払い型の保証料は負担に映るかもしれません。なお、保証料をローンに組み込んで借入額を増やすことは通常できない(認めない銀行が多い)ので、自己資金として用意が必要です。この初期負担の大きさが外枠方式のネックと言えます。ただし、そのぶん前述のメリットで総支払額は低めに抑えられるので、初期費用と長期コストのバランスを考えて選択しましょう。
内枠方式(後払い型)の仕組み
内枠方式とは、保証料をローン金利に上乗せして毎月支払う方式です。利息上乗せ型とも呼ばれ、契約時に保証料を現金で支払う必要がありません。具体的には、適用金利に所定の上乗せ金利(保証料率)をプラスしてローン返済していきます。多くの金融機関では上乗せ幅は年0.2%程度に設定されており、たとえば通常金利年0.6%のローンなら内枠方式では年0.8%(0.6%+0.2%)の金利になります。これにより保証料が利息の一部として毎月少しずつ支払われるイメージです。
内枠方式のメリット
内枠方式のメリットは、契約時の手持ち資金負担を抑えられることにあります。保証料を別途用意しなくて良いため、頭金や諸費用で手一杯という場合でも導入しやすい方式です。「住宅購入で貯金をほとんど使ってしまい、保証料まで払えない…」というケースでは内枠方式が資金計画上の助けになるでしょう。また、保証料を金利に含めることで支払いが見えづらくなり心理的負担が軽いという感じ方をする方もいます(「保証料0円」と表示されることもあり、一見費用がかからない印象になります)。
内枠方式のデメリット
内枠方式のデメリットは、総返済額が外枠方式より大きくなりやすい点です。保証料分にも利息がかかる形になるため、結果的に一括前払いより支払い総額が割高になります。先ほどの例で、3,000万円35年ローンのケースを試算すると、外枠方式なら保証料約66万円(概算)なのに対し、内枠方式では金利上乗せ分として総額114万円程度多く支払うことになります。これは長期間利息を払い続ける影響です。よって、一括で支払う保証料(約66万円)より長期で金利に上乗せした保証料(約114万円)の方が多く保証料を支払う事となります。
保証料ゼロ型(保証料ゼロ表記)の実態
保証料ゼロ型とは、基本的には前述の内枠方式と同様に保証料を金利に含めて支払うまたは事務手数料として支払うタイプです。銀行によっては「保証料0円」「保証料不要」といった表記で案内されることもありますが、その実態は保証料が完全にタダになるわけではなく、別の形でコストを負担している点に注意しましょう。多くの場合、保証料ゼロ型とは保証会社を利用せずに保証料0円とする代わりに、ローン金利を通常より高めに設定する方式を指します。実質的には保証料分を利息として支払っている構造もあり、内枠方式とほぼ同義と考えて差し支えありません。
ここで誤解のないように言っておきますが、保証料の負担を契約者には求めず、あくまでも金融機関が負担となっています。但し、適用される金利が若干高かったり、別の名目(事務手数料など)を多く徴収したりすると言った形です。
ただし「保証会社を利用しない」ローンには2通りあります。一つは銀行自身がリスクを負う代わりに金利を上乗せするケース、もう一つは保証料ではなく融資事務手数料として別途徴収するケースです。前者の場合、形式上は保証会社を介さないため保証料0円ですが、銀行が想定リスク分だけ金利を高めに設定しています(例:通常金利+0.2%など)。後者の場合、次章で解説する「融資手数料型」に近く、保証料が無料な代わりに契約時に数%の事務手数料を支払う形です。いずれにせよ、「保証料ゼロ」の文字だけで飛びつくのではなく、どこにコストが転嫁されているかを見極めることが大切です。
保証料ゼロ型のメリット
保証料ゼロ型のメリットは、一見諸費用が安く感じられる点と、内枠方式と同じく初期費用の負担が小さい点です。保証料を別途用意しなくて良いので、手元資金が少ない契約者でも契約しやすくなります。また「保証料無料」という響きから、心理的ハードルが下がる効果もあります。さらに、保証料ゼロ型の場合は実際に保証会社を利用しないケースもあるため、保証会社の審査が省略され手続きが簡素な場合もあります(銀行独自審査のみで済む場合など)。ただし、この審査簡略化は金融機関によって異なるため、一概には言えません。
保証料ゼロ型のデメリット
保証料ゼロ型のデメリットも、基本的には内枠方式と共通です。まず、ローンの総支払額が割高になりやすいこと。保証料0円の代わりに高めの金利をずっと払い続けるため、結果的に外枠方式より多くの利息を支払う可能性が高いです。また事務手数料型であった場合、途中完済しても保証料相当の返金はありません。さらに、金融機関によっては金利上乗せ型=融資手数料型となっており、借入時に高額の事務手数料(借入額の○%)を支払うケースもある点に注意が必要です。この場合、「保証料0円」という宣伝文句に反して契約時の出費はそれほど減らないという落とし穴があります。
要するに、保証料ゼロ型は言葉が悪いですが「保証料を隠れコスト化した方式」とも言えます。実態を理解せずに飛びつくと、後から『思ったより総支払いが多い…』と感じるリスクがあります。特に借入期間が長期になるほどデメリットが大きくなる点は留意しましょう。メリット・デメリットとも内枠方式と似ていますが、保証料ゼロ型特有の宣伝に惑わされず、冷静にトータルコストを比較することが大切です。
ケース別シミュレーションで見る総支払額の差
それでは、外枠方式・内枠方式・金利上乗せ型でどのくらい総支払額に差が出るのか、ケース別にシミュレーションしてみましょう。ここでは分かりやすくするために、保証料ゼロ型=内枠方式(保証料を金利に含める)とみなして比較します。また、新たに保証料不要の融資事務手数料型についても併せて触れ、合計4パターンで検証します。
ケースA:35年完済の場合(借入額3,000万円、金利はどの方式でも実質同程度と仮定)
- 外枠方式:契約時に保証料約66万円を支払い、利息は通常金利分のみ。
→ 保証料総額:約66万円(一括払い)、利息総額:通常金利分のみ。
- 内枠方式:保証料相当を年0.2%金利上乗せで支払い。
→ 保証料総額:約114万円(利息に含む)、利息総額:通常金利+0.2%分。
- 保証料ゼロ型:内枠方式と実質同じ(保証料0円表記だが実質適用金利+0.2%)。
→ 保証料総額:約114万円(利息に含む)、利息総額:通常金利が少し高め。
- 融資手数料型(事務手数料型):保証料不要だが融資手数料2.2%(税込)を支払い。
→ 手数料:約66万円(借入時一括)、利息総額:通常金利分のみ。
≪結果≫ 最も総負担が少ないのは外枠方式(保証料約66万円)と融資手数料型(約66万円)であります。内枠方式と金利上乗せ型(約114万円)は保証料部分だけで外枠の2倍近い負担となり、35年完済前提では割高になることが分かります。但し、融資手数料型(事務手数料型)以外は、保証料以外に事務手数料(定額型)が、約3万円~5万円程度かかります。
ケースB:10年で繰上返済した場合(※途中完済し、残債ゼロになったケース)
- 外枠方式:保証料約66万円を支払っていたが、残り25年分に相当する戻し保証料が完済時に返金される。
→ 戻し保証料:例えば約46万円(返金額は保証会社計算式による)、実質負担:約20万円。
- 内枠方式:10年間金利0.2%上乗せで払い、その後完済。以降の保証料支払いは不要だが過去分は戻らない。
→ 支払済保証料相当:約33万円弱(0.2%上乗せ分×12ヶ月×10年)、返金:0円。
- 金利上乗せ型:内枠方式と同様、支払済保証料相当:約33万円、返金:なし。
- 融資手数料型:契約時に支払った手数料66万円は戻らない。完済で利息軽減はできても手数料の返金は無し。
≪結果≫ 短期間でローンを完済した場合、外枠方式は大半の保証料が戻ってくるため実質負担がごく小さい(約20万円)ことが分かります。一方、内枠方式や金利上乗せ型は途中までの支払い分がそのままコストとなり、10年間で約46万円前後を支払ったままになります。融資手数料型は契約時の66万円がまるごと固定費としてかかり、早期完済すると相対的に割高になってしまいます。このケースでは外枠方式が圧倒的に有利と言えるでしょう。
各方式のメリット・デメリットまとめ
|
保証料(外枠方式) |
保証料(内枠方式) |
事務手数料型 |
|
|
返済期間 |
返済期間が長くなる |
金利がかかるため、返済期間により返済総額がかわる |
定率のため返済期間の |
|
繰り上げ返済 |
返済期間短縮により |
分割払いのため返金はない |
返済期間短縮による |
|
自己資金 |
一括支払いのため準備が必要 |
月々返済するため不要 |
一括支払いのため準備が必要 |
以上のシミュレーションから、「長期でゆっくり返済するなら融資手数料型や外枠方式、早期返済の可能性が高いなら外枠方式が最も有利」という傾向が見て取れます。逆に、「毎月の負担をとにかく抑えたい」「手元資金が少ない」という場合は内枠方式(または保証料ゼロ型)を選ぶ価値があります。重要なのは、自分の返済計画やライフプランに合わせて最適な方式を選ぶことです。次章からは、保証に関するその他の論点(保証会社や連帯保証人、保証料の節約策など)について解説していきます。
保証会社の役割と審査ポイント――連帯保証人との決定的な違い
前章までは保証料とその支払い方式に注目しましたが、その保証を実際に引き受ける「保証会社」についても理解しておきましょう。保証会社とは文字通り住宅ローンの保証を専門に行う会社であり、銀行の代わりに契約者の信用リスクを負います。銀行で住宅ローンを組む際はこの保証会社を利用するのが一般的で、契約者は保証会社に保証料を支払い、保証会社は契約者が返済不能になったとき代わりに返済するという役割分担です。
保証会社の存在により、契約者は基本的に親族などの連帯保証人を立てなくてもローンを借りられるようになりました。これは大きなメリットですが、契約者として押さえておきたいポイントもあります。以下では保証会社の具体的な役割(代位弁済)や、主要な保証会社の一覧と特色、そして保証会社の審査が「厳しい」と言われる理由と対策について解説します。併せて、保証会社利用と連帯保証人制度の違いも見ていきましょう。
保証会社が行う「代位弁済」とは
代位弁済(だいいべんさい)とは、前述のとおり保証会社が契約者に代わって銀行にローン残債務を一括返済することです。契約者が返済不能に陥った場合に初めて実行される措置で、保証会社の最も重要な役割と言えます。代位弁済が行われると、契約者に対する債権者が銀行から保証会社に切り替わります。つまり保証会社が銀行に立て替えた後、契約者は保証会社にその代位弁済分を返済していく義務を負うことになります。
代位弁済が行われた場合の留意点として、契約者の信用情報にその事実が記録されることが挙げられます。ローンの延滞や代位弁済の履歴は信用情報機関に登録され、一定期間、新規の借入やクレジットカード作成が困難になるなどの不利益が生じます。また代位弁済後も債務そのものは免除されないため、契約者は保証会社から厳しく返済を求められる立場となります。最悪の場合、保証会社が契約者の住宅など資産に対して法的手続きを取ることもあり得ます。
以上からお分かりのように、保証会社による代位弁済は契約者にとっても大変な事態です。保証料を払っているからといって安心せず、代位弁済を避けるよう計画的な返済を心がけましょう。保証会社はあくまで銀行への支払いを肩代わりしてくれるだけで、契約者自身の債務が帳消しになるわけではない点を改めて強調しておきます。
主な保証会社一覧と特色
日本には多数の保証会社がありますが、大きく分けて2種類に分類できます。一つは銀行系列の保証会社、もう一つは独立系の保証会社です。
- 銀行系列の保証会社
メガバンクや地方銀行は、自社グループ内に住宅ローン保証専門の子会社・関連会社を持っていることが多いです。具体例を挙げると、三菱UFJ銀行系列の「三菱UFJローンビジネス」、みずほ銀行系列の「みずほ信用保証」、三井住友銀行系列の「SMBC信用保証」、りそな銀行系列の「りそな保証」などがあります。これらは各銀行の顧客向け住宅ローンを主に保証しており、提携先金融機関が限定される傾向があります。
- 独立系の保証会社
特定の金融グループに属さず、全国の複数金融機関と提携して保証業務を行う会社です。代表的なのが「全国保証株式会社」で、全国の地方銀行・信用金庫など多数の金融機関の住宅ローン保証を手掛けています。全国保証は取り扱い規模も大きく、住宅ローン残高17兆円超を保証する国内最大級の保証会社です。また、住宅金融支援機構の【フラット35(保証型)】にも対応しているのが特色です。
その他、クレジット会社系(例:オリコやセディナが保証業務を行うケース)や、信託銀行系の保証会社、信用金庫・JA系列の保証機関なども存在します。自分が住宅ローンを申し込む金融機関で、どの保証会社を利用するかは事前に確認できます。多くの場合、銀行の担当者から「保証会社○○の保証審査があります」と説明されるでしょう。保証会社によって審査基準や保証料率が微妙に異なることもありますが、基本的な役割はどこも同じです。
審査が厳しいと言われる理由と対策
住宅ローンの審査では、銀行の審査と並んで保証会社の審査も行われます。しばしば「保証会社の審査は厳しい」と耳にすることがありますが、その理由は何でしょうか? まず、保証会社は自社が肩代わり返済するリスクをチェックする立場です。銀行以上にシビアな目で申込者の返済能力や信用状況を見極めようとするため、審査基準が厳格になる傾向があります。
具体的には、保証会社の審査では申込者の年収・勤続年数・他債務状況・過去の延滞履歴などが細かく調べられます。特に過去にクレジットやローンの支払い延滞があると、信用情報上でマイナスとなり審査通過は難しくなります。また、借入希望額が年収に対して過大(返済比率超過)でないか、勤続年数が極端に短くないか、自営業者なら収入が安定しているか、といった点も厳しく見られます。保証会社にとっては、審査を通した人が将来返済不能に陥ると自社の損失になるため、慎重になるのは当然なのです。
では、保証会社の審査に通るためにどんな対策があるでしょうか?基本的には銀行の審査対策と同じですが、以下のポイントに留意すると良いでしょう。
- 信用情報をクリーンに保つ
携帯電話の分割払いを含め、過去のあらゆる支払いを滞納しないようにします。万一過去に延滞がある場合でも、それから一定年数経過すれば情報は消えるので、新規申し込みはそれまで待つのも一策です。
- 他の借入を整理する
カードローンやリボ払い残高が多いと審査でマイナスです。可能な限り事前に完済・解約し、借入件数・残高を減らしておきましょう。車のローンなど大口債務も返せるものは返済してから臨む方が有利です。
- 収入合算や物件共有を検討
単独では返済比率がオーバーしそうな場合、配偶者の収入合算やペアローンで連帯保証人(連帯債務者)になってもらう手もあります。こうすることで返済負担率を引き下げ、審査通過の可能性を高められます。ただし相手にも責任が及ぶので慎重に。
- 頭金を増やす・借入額を抑える
希望額ギリギリではなく、無理なく返せる範囲に借入額を抑えます。たとえば物件価格の2割を頭金として入れるだけでも印象は良くなります。保証会社もリスクが減るため前向きに検討してくれるでしょう。
- 属性を整える
転職・独立は可能ならローン審査後まで待つ、勤続年数をもう少し積む、正社員登用を目指すなど、申込時の属性をできるだけ安定した状態にしておくことが理想です。
以上のような対策を講じれば、「保証会社の審査が厳しい」と言われる中でも通過率を上げることができます。とはいえ、現実には保証会社の審査に落ちるケースもあります。その場合でも金融機関によっては他の保証会社で再審査してくれたり、保証会社を使わない別商品の提案があったりするので、諦めず相談してみましょう。重要なのは、自分の信用力や返済計画に見合った借入を心掛けることです。そうすれば保証会社もきっと味方になってくれるはずです。
連帯保証人が必要になるケースを解説!保証人制度のリスクとメリット
「住宅ローンは保証会社に任せれば連帯保証人はいらない」と言われますが、実はケースによっては連帯保証人が必要になる場合もあります。この章では、どんな場合に連帯保証人が求められるのかを代表的なケースで見てみましょう。また、連帯保証人を立てることのリスクとメリットについても解説します。保証会社による保証との違いを理解するためにも、連帯保証人制度のポイントを押さえておきましょう。
【連帯保証人とは】 主たる債務者(ローン契約者)が返済できなくなったときに、代わりに全額返済する義務を負う人を指します。通常の保証人と違って「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という逃れられる権利がなく、契約者とほぼ同等の返済義務を負う非常に重い立場です。簡単に言えば、契約者が払えないとき無条件で肩代わりしなければならない人──それが連帯保証人です。
・催告の抗弁権とは?
保証人に債務の請求が来た場合に先に債務者に請求を行うよう抗弁できる保証人の権利です。
・検索の抗弁権とは?
保証人に債務の請求が来た場合に先に債務者の財産に執行せよと抗弁できる保証人の権利です。
・分別の利益とは?
同一の主たる債務を複数名の保証人によって保証する場合、それぞれの保証人が追う債務は主たる債務を保証人の頭数で割ったものにとどめるというものです。
連帯保証人には、これらの権利が無く、とても重たい責任が付いて回ります。
連帯保証人が必要となる主なケース
現代の住宅ローンでは単独で借りる場合、原則連帯保証人は不要です。しかし、以下のようなケースでは金融機関から連帯保証人を求められることがあります。
- ケース1:夫婦・親子で収入合算する場合
住宅ローンの借入可能額を増やすために、夫婦や親子の収入を合算して申し込むケースがあります。収入合算には「連帯債務型」と「連帯保証型」がありますが、一方が債務者、もう一方がその連帯保証人となる方法(連帯保証型)では保証人となる配偶者や親に連帯保証義務が生じます。例えば、妻の収入を合算して夫名義で借りる場合、妻が連帯保証人になるという形です。この場合、妻はローン債務者ではありませんが、夫が返せなくなれば夫と同じ責任で返済を求められます。
- ケース2:ペアローンを利用する場合
夫婦それぞれがローンを組み、お互いがお互いの連帯保証人になるのがペアローンです。一本のローンを共同で返す連帯債務型と違い、ローン契約が2本存在するため、それぞれが相手のローンの保証人という位置付けになります。この場合も、どちらか一方が返せなくなれば連帯保証人である配偶者に残債全額の返済義務が及びます。ペアローンは双方が主債務者にもなる分、責任も双方に同等に発生する点に注意が必要です。
- ケース3:物件を夫婦共有名義にする場合
夫婦で物件を共有名義にする(持分を分ける)と、ローン債務者の単独名義に比べて担保価値の把握が難しくなるため、金融機関は共有者にも保証を求めることがあります。たとえば夫婦それぞれ資金を出し合って共有名義にした場合、ローン契約者ではない方(配偶者)が連帯保証人になるよう求められるケースが多いです。これは共有者が連帯保証することで、銀行としては物件全体を担保に取ったのと同等の安全性を担保する狙いがあります。なお、収入合算せず共有名義にする場合は、共有者を物上保証人(担保提供者)とする扱いに留める金融機関もあります。物上保証人は担保提供のみで返済義務は負いませんが、一般的には連帯保証人を立てるケースの方が多いようです。
以上が主なケースですが、この他にも借入額が希望額に対し多すぎる場合や契約者の属性に不安がある場合に、銀行から連帯保証人の追加を求められる例があります。たとえば自営業で業績が不安定な場合に配偶者を保証人に立てる、勤続年数が極端に短い場合に親を保証人に立てる、といったケースです。ただし、昨今は保証会社制度が普及したため、銀行側も極力連帯保証人を立てずに済む方法を考えてくれることが多くなっています。実際、「住宅ローン契約時に連帯保証人を取られるケースは少なくなった」と言われています。念のため、加筆しておきますが、ここに書いたケースがすべて連帯保証人を求められると言う訳ではありません。各々の金融機関・保証会社の基準に基づきますので、事前に相談・確認することをおすすめします。
連帯保証人のリスクとメリット
連帯保証人の最大のリスクは、その責任の重さにあります。連帯保証人になるということは、巨額のローン債務を自分ごととして背負うのと同義です。契約者に万一のこと(返済不能状態)があれば、どんな事情があろうと保証人が返済を求められます。自分はお金を借りてもいないのに、突然何千万円もの請求が降りかかる可能性があるのです。これは家族間であっても大変な負担であり、返済できなければ保証人自身の財産や信用も失うリスクがあります。実際、連帯保証が原因で家族関係が悪化したり、保証人が自己破産に追い込まれたりするケースも社会問題となってきました。
また、連帯保証人は住宅ローン控除(税額控除*の適用も受けられませんし、団体信用生命保険(団信)にも加入できません。ローン名義人(債務者)のみが住宅ローン減税や団信の恩恵を受け、保証人はメリットなしにリスクだけ負う形です。例えば夫が債務者・妻が連帯保証人のケースでは、妻は住宅ローン減税も効かず、夫に万一のことがあっても団信でローンがゼロになるわけではない(夫死亡時は団信でローン返済→保証債務消滅となるが、自身は保険対象ではない)といった具合です。つまり連帯保証人には直接的な経済メリットは基本的に無いのです。
ではメリットは皆無かというと、直接的ではないものの連帯保証人を立てることで借入が可能になる/増額できるという効果があります。保証人がいるからこそローン審査に通り、念願のマイホームを取得できるというケースは確かに存在します。特に親が子を保証する場合、「子どもの住宅取得を助けてあげられる」という家族的メリットを感じるかもしれません。また夫婦間では、一方が保証人になることで配偶者の収入も評価されより大きな額を借りられるメリットがあります。要は、連帯保証によって融資の道が開ける/選択肢が広がるという間接的メリットがあるわけです。
総合すると、連帯保証人制度はメリットよりリスク・負担が大きいのが実情です。保証会社に保証料を払ってでも保証人を避けたいという流れになっているのも、そのためでしょう。仮に連帯保証人を引き受ける場合は、家族間できちんと話し合い、万一の際の対応策(生命保険の加入や保証人を外れる条件設定など)も検討しておくことをおすすめします。保証会社との違いをまとめると、保証会社=お金でプロにリスクを負ってもらう、連帯保証人=無償で身内にリスクを負ってもらうという点に尽きます。どちらが良い悪いではなく、状況に応じた選択をすることが大切です。
我々の世代(50代)においては、子供の頃から親に『アンタ!(連帯)保証人になんか、絶対になったらアカンで!』とお金にまつわるニュースなどが流れるたびに言われたものです。
その当時は、保証人・連帯保証人の意味など分かっていませんでしたが、保証人になれば自分の人生が詰んでしまう恐れがあると子供ながらに思ったものです。
保証料を節約する5つの具体策
住宅ローンの保証料は高額になりがちな費用ですが、工夫次第で節約することも可能です。ここでは保証料負担を少しでも減らすための5つの具体的な方法をご紹介します。繰上返済の活用から金融機関選びまで、できる対策はしっかり押さえておきましょう。
繰上返済による保証料返戻金の仕組み
繰上返済とは、予定より早くローンの一部または全額を返済することです。実は繰上返済をすると、前払いした保証料の一部が戻ってくる場合があります。これが「保証料返戻金(戻し保証料)」の仕組みです。
具体的には、外枠方式で一括前払いした保証料について、借入期間が短縮された分を後日清算して返金してもらえるものです。例えば35年分の保証料を払っていたのに25年で完済した場合、残り10年分相当の保証料が所定の計算式で算出され、差額が返金されます。各保証会社で計算方法は異なりますが、簡単に言えば「未経過期間の保証料は返す」という考え方です。
返金のタイミングは金融機関によりますが、多くは繰上返済や完済を行った後、1ヶ月以内程度で指定口座に振り込まれます。なお、返戻には保証会社の事務手数料(1万円前後)が差し引かれるのが一般的です。少額の返戻金だと手数料に満たず戻らない場合もあるので注意しましょう。
重要なのは、この返戻制度は外枠方式(前払い)で保証料を支払った場合のみ適用される点です。内枠方式や金利上乗せ型では、そもそも前払いしていないので返戻金は発生しません。したがって、「将来まとまった繰上返済をするかもしれない」という人は、外枠方式を選んでおいた方が結果的に保証料を節約できる可能性があります。
繰上返済を活用することで、支払った保証料の一部が戻ってくるメリットをぜひ享受しましょう。
借換えで保証料を減らすテクニック
金利低下時には住宅ローンの借換え(借り換え)を検討する方も多いでしょう。借換えによって利息を減らせるのはもちろんですが、保証料の面でも節約効果が期待できます。
まず、現在外枠方式で保証料を支払っている場合、借換えにより既存ローンを一括返済すると前述の戻し保証料が返ってきます。例えば当初60万円払った保証料のうち、残期間分として30万円戻ってくれば、それが借換えの原資の一部にもなります。この返戻金は忘れずに受け取りましょう。
次に、借換え先のローン選びがポイントです。保証料が不要のローンを選べば、新たな保証料負担を回避できます。近年はネット銀行を中心に保証料ゼロの住宅ローンが増えています(代わりに融資手数料がかかる)。例えばPayPay銀行や住信SBIネット銀行、ソニー銀行などは保証料・印紙税がかからず借換え時の諸費用を低く抑えられるので、トータルコスト削減に有効です。
一方で、借換え先でも保証料型のローンを選ぶ場合は再度保証料が発生します。銀行が変われば保証会社も変わるため、残念ながら以前払った保証料を引き継ぐことはできません。従って、保証料型→保証料型の借換えは二重に保証料を払うことになる点に注意です。その場合でも、前のローンの返戻金と新たな保証料を差し引きしてプラスであれば問題ありませんが、保証料負担が重なり借換えメリットを打ち消す可能性もあります。試算してみてメリットが薄ければ無理に借換えない方が良いでしょう。
借換えを検討する際は、金利差による利息軽減だけでなく、保証料や手数料を含めた総費用で比較することが大切です。借換えで保証料を節約するコツは、「保証料返戻金を得て、なおかつ新ローンで保証料を払わない/少なくする」という点にあります。複数の金融機関で諸費用シミュレーションを行い、総支払額が最小になる組み合わせを見つけましょう。
金融機関選びで変わるコスト差
実はどの金融機関でローンを借りるかによって、保証料のコストには大きな差が生じます。各銀行・保証会社で保証料率は異なり、同じ借入条件でも数十万円単位で差がつくこともあります。したがって、金融機関選び自体が保証料節約の鍵と言えます。
具体例を挙げると、ある銀行Aでは「100万円借入あたりの保証料=2万円(35年の場合)」という設定で、3,000万円借入なら60万円の保証料になります。一方、銀行Bでは「保証料率1.5%」という設定で、同じ3,000万円でも45万円程度で済むかもしれません。さらには銀行Cでは「保証料0円・融資手数料型」で保証料負担ゼロだけど手数料が2%(60万円)かかる、といった具合です。各行の公式サイトや比較サイトで保証料率を調べると、この違いが見えてきます。
また、メガバンクより地方銀行やネット銀行の方が、保証料が安い場合もあります。例えば地方銀行の中には「住宅ローン保証料は他行より低率」というのを売りにしているところもあります。逆にネット銀行では保証料自体を取らず融資手数料型にしているケースが多く、保証料負担という概念がありません。いずれにしても、事前に複数の金融機関の試算を比較することが重要です。
さらに、提携ローンや勤務先提携による優遇も見逃せません。住宅メーカー提携ローンでは保証料が割安になったり、勤務先企業がメガバンクと提携していて保証料○割引になったりするケースもあります。こうした優遇制度を利用すると数十万円のコスト減につながることもあります。自分が該当する優遇がないか、金融機関や不動産会社に確認してみましょう。
結論として、「どこで借りるか」で保証料コストは大きく変わるため、金利だけでなく保証料まで含めたトータルでお得な金融機関を選ぶことが保証料節約につながります。時間と手間はかかりますが、その価値は十分にあるはずです。
団信込みローンとトータルコスト比較
住宅ローンのコストを考える上で、団体信用生命保険(団信)の扱いも含めて総合的に比較することが大切です。団信はローン契約者が死亡または高度障害になった場合に残債がゼロになる保険で、多くの銀行ローンでは加入が必須です。通常、銀行が団信保険料を負担し金利にそのコストを含めている場合がほとんどです。つまり団信保険料は実質的に住宅ローン金利の一部という形になっています。
団体信用生命保険(団信)についてはコチラ⇒不動産購入前に知っておきたい!住宅ローン団体信用生命保険の基本!
一方、フラット35など一部のローンでは団信が任意加入で、保険料は契約者負担(別払い)となっています。団信に入らない選択もできますが、入る場合は毎年数万円程度の保険料を別途支払う必要があります。たとえばフラット35では借入額や年齢に応じて保険料が決まり、金利換算すると年0.3%弱程度と言われます。
なぜ団信の話が保証料節約に関係するかというと、総支出で考えると保証料・手数料と団信保険料はトレードオフになる場合があるからです。例えば、あるネット銀行のローンは「保証料0・団信無料(銀行負担)・手数料2%」で、金利0.5%とします。一方、フラット35は「保証料0・手数料数十万円・団信保険料自己負担・金利1.3%」とします。単純比較では金利はネット銀行が安いですが、フラット35は団信保険料を自分で払う必要があります。その費用まで含めて考えると、ネット銀行ローン(団信込み)とフラット35(団信別)のどちらがトータル安いか判断が必要です。
また、銀行ローンでも「ワイド団信(疾病保障付き)」など特約を付けると金利+0.2~0.3%上乗せされることがあります。これも一種の保険料負担増です。保証料型 vs 手数料型を比較する際は、同じ条件で団信特約の有無も揃えて比較しないと正確なコスト差が見えません。
要するに、保証料/手数料と団信保険料を合わせてトータルコストを比較することが大事ということです。極端な例を言えば、「保証料0・団信有料」のローンと「保証料あり・団信無料」のローンでは、一方は保証料、もう一方は保険料という違いがあるだけで支払い先が違うだけの可能性もあります。ぜひ諸費用と金利、保険料すべてを含めて総合的にシミュレーションし、自分に有利なローンを選びましょう。
キャンペーン・優遇制度の活用法
最後に、金融機関のキャンペーンや公的優遇制度を活用して保証料を節約する方法です。住宅ローン業界は競争が激しいため、各銀行が様々なキャンペーンを展開しています。その中には保証料に関する優遇も見られます。
例えば、ある銀行では「〇〇キャンペーン期間中に申し込めば保証料○%割引」や「WEB契約なら保証料半額」といったプロモーションを行うことがあります。また、都市銀行ではなかなかありませんが、信用金庫や地方銀行で「〇歳未満の子育て世帯は保証料優遇」といった地域独自の制度がある場合もあります。ご自身が利用できるキャンペーンがないか、事前に金融機関のサイトやニュースリリースをチェックしてみましょう。
公的な優遇制度としては、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)が代表的ですが、これは保証料直接ではなく年末残高に対する減税です。ただ、前述したように保証料を金利に組み込んでいる場合は、その分住宅ローン減税で控除される金額が増えるため、結果的に保証料負担が軽減される効果があります(減税額がその分わずかに増える)。この制度は誰でも使えますので、忘れずに適用を受けましょう。
他にも、自治体によっては住宅取得支援策で利子補給や補助金が出る場合があります。例えば子育て支援や移住支援で利子補給があると、実質金利が下がり保証料負担の実質も下がるようなものです。直接「保証料」を狙ったものではありませんが、総返済負担を減らせる制度は結果として保証料負担軽減につながります。
銀行の提携割引も見逃せません。前述のように、勤務先企業や団体と銀行が提携していると保証料〇%オフなどの特典があります。また、給与振込やクレジットカード契約など複数の条件を満たすと金利優遇や手数料優遇が受けられるパッケージもあります。そうしたセット契約での優遇を利用すれば、保証料そのものではなくても利息負担を下げ、トータルコストを減らせます。
このように、あらゆるキャンペーンと優遇を総動員することで保証料負担を間接的にでも減らすことが可能です。住宅ローン契約前には、銀行の情報を集め、使えるものは積極的に使いましょう。「塵も積もれば山となる」で、数万円~十数万円規模の節約につながることもあります。
私の場合は保証料少し得をしました
私自身も住宅ローン経験者(現在も返済中)です。当時は外枠方式(前払い)で保証料を納めましたが、返済方法は元金均等返済を選択しました。数字はもう15年以上前で正確には覚えていませんが、担当者から受けた説明は今でも印象に残っています。
「元金均等返済は、元利均等返済より元本が早く減るぶん、保証会社が負う債務も早く小さくなります。だから保証料が割安になるんですよ」
つまり、元本の返済スピードが速いほど保証会社のリスクが短期間で縮まるため、私のケースでは保証料を抑えられた、というわけです。
よくあるQ&A:申し込み前に知っておきたい保証料・保証会社の疑問点
最後に、住宅ローンの保証料や保証会社に関してよくある質問とその回答をまとめました。申し込み前の疑問点をここで一気に解消しておきましょう。
Q1. 保証料を払えば連帯保証人は絶対いらないの?
A1. 原則はいりませんが、収入合算や特殊な事情では連帯保証人が必要になる場合があります。基本的に保証会社が保証人の代わりを務めるため、単独ローンなら保証人不要です。しかし「夫婦で収入合算する」「親子で共有名義にする」等では、配偶者や親が連帯保証人になるケースがあります。事前に金融機関に条件を確認しましょう。
Q2. 保証料は誰に支払うの?銀行?保証会社?
A2. 実務的には銀行が預かり、保証会社に支払います。契約者は銀行経由で保証料を払い、銀行が提携する保証会社との契約に基づきその保証料が渡ります。契約者と保証会社は保証委託契約で直接つながりますが、お金の流れは銀行経由と考えて構いません。したがって保証料の領収証等は銀行から発行されることが多いです。
Q3. 保証会社の審査と銀行の審査は別々にあるの?
A3. はい、保証会社審査は銀行審査と並行して行われます。多くの場合、銀行にローン申し込みをすると同時に保証会社にも審査書類が回ります。一体化しているように見えますが、実際には銀行審査に加え保証会社の独自審査があると考えてください。どちらか一方でもNGならローン承認は下りません。保証会社審査では信用情報や返済負担率など厳しくチェックされます。
Q4. 保証会社からも直接審査の問い合わせが来るの?
A4. 通常、保証会社が直接本人に連絡することはありません。審査過程で追加資料や確認事項があれば、銀行の担当者を通じて依頼されます。保証会社名義で郵送物が届くことも基本ありません。ただし、審査可決後に保証委託契約書への署名捺印は必要です。これは銀行での契約手続き時に行います。
Q5. 「保証料0円」と書かれたローンは本当にタダなの?
A5. 保証料自体は0円でも、別の形で費用負担しています。多くの場合、保証料0円のローンは融資手数料型や金利上乗せ型(適用金利が元々少し高めに設定)であり、高い事務手数料や若干高めの金利を支払うことで保証料を相殺しています。決して銀行がボランティアで保証コストをタダにしているわけではありません。総支払額で見れば他のローンと同程度か、場合によっては高くつくこともあります。「保証料無料」の宣伝文句だけに惑わされず、内訳を確認しましょう。
Q6. フラット35には保証料がないと聞いたけど?
A6. はい、フラット35は保証料不要です。その代わり民間の保証会社を使わず、住宅金融支援機構が貸し倒れリスクをカバーする仕組みになっています(機構が保険金を支払う形)。ただしフラット35は融資手数料が借入額の2%前後かかり、団信保険料も自己負担なので、保証料がない分他の費用がかかると考えてください。トータルコストで比較することが重要です。
Q7. 保証料はローン控除や経費にできるの?
A7. 住宅ローン減税の控除対象にはなりません。住宅ローン減税は年末借入残高の1%を所得税控除する制度で、借入残高に対してです。保証料は利息ではなく手数料扱いのため、この減税の直接の対象ではありません。ただし前述のように保証料を金利に含めた場合は結果的に(金利上昇分わずかに元本の減りが遅くなるから)控除に反映されます。なお、賃貸用不動産ローンなら保証料は必要経費計上できますが、マイホームの保証料は所得控除などの制度は特にありません。
Q8. 繰上返済したら保証料が戻るって本当?
A8. 本当です(外枠方式の場合)。一括前払いした保証料は、ローン期間短縮分に応じて「戻し保証料」が返金されます。実行日から完済日までの未経過期間分が計算され、所定の事務手数料を差し引いて返ってきます。ただし内枠方式や金利上乗せ型では対象外なので注意してください。繰上返済をした後に銀行に問い合わせれば、どのくらい戻るか試算してくれます。
Q9. 保証会社が代位弁済したら、もう自分は払わなくていいの?
A9. いいえ、返済義務は消えません。保証会社が銀行に一括返済してくれるため銀行への債務はなくなりますが、今度は保証会社に同額の債務を返す義務が生じます。むしろ保証会社の方が厳しく取り立ててくる可能性もあり、延滞情報も信用機関に登録されます。保証会社の代位弁済はあくまで銀行を救済する仕組みで、契約者が救済されるわけではない点に注意しましょう。
Q10. 万が一自己破産したら保証料は返ってくる?
A10. 保証料は返金されません。自己破産すると債務は免責になりますが、過去に支払った保証料が戻ることはありません。一度支払った保証料はサービス提供の対価として消費されており、破産しようとしまいと契約終了まで返らないのが原則です。ただし、破産手続き中に保証会社が代位弁済した場合、保証会社が債権者として破産債権を届け出る形になります。いずれにせよ契約者に保証料が戻ることは期待できません。
Q11. 保証会社と保証人、どちらが良いの?
A11. 一般的には保証会社の方が安心です。保証会社はプロであり、契約者は保証料を払うだけで人間関係のトラブルなく手続きできます。一方、連帯保証人は親族とはいえ無償で多大なリスクを負わせることになるので、お互い心理的負担が大きいです。最近の住宅ローンは保証会社利用が主流で、金融機関も保証人より保証会社を求める傾向です。ただし、収入合算などで保証人を立てるメリットもあるので(借入可能額増加など)、状況次第では検討となります。
Q12. 一度払った保証料を、後から内枠に変更して返してもらうことはできる?
A12. できません。契約時に外枠か内枠か方式を選択したら、途中で変更は基本的に不可能です。途中で内枠→外枠に変更して一括で払う、逆に外枠→内枠に変更して返金を受ける、といった柔軟な仕組みは用意されていません。どうしても変更したければローンを借り換えるしかありません。したがって、最初の契約時によく検討して決める必要があります。
まとめ&チェックリスト:あなたに最適な保証方式を選ぶステップ
住宅ローンの保証料・保証会社・保証人制度について、初歩から具体策まで幅広く見てきました。最後に重要ポイントを振り返りつつ、自分に最適な保証方式を選ぶためのチェックリストを示します。

<まとめ>
保証料とは住宅ローン返済不能時に備えて保証会社に支払う費用であり、契約者の返済義務自体をなくすものではありません。保証料の支払い方法には外枠(前払い)・内枠(利息上乗せ)・融資手数料型があり、それぞれ初期負担や総支払額に違いがあります。保証会社は銀行のリスクヘッジとして重要な役割を果たし、契約者は保証料を払うことで基本的に連帯保証人を免除されます。ただし、ケースによっては連帯保証人が必要になることもあり、その責任は非常に重いです。保証料負担を減らすには繰上返済による保証料返戻や借換え、金融機関選びや各種優遇の活用が有効です。そして「保証料不要」のローンも含め、常にトータルコストで比較検討することが肝心です。
それでは、あなたに最適な保証方式を選ぶためのチェックリストを確認しましょう。以下のステップに沿って検討すれば、自ずと最適解が見えてくるはずです。
- 資金計画の確認
住宅購入に充てられる頭金・諸費用の自己資金はいくらあるか? 契約時に保証料や手数料を一括で用意できる金額を把握します。手元資金に余裕がない場合は内枠方式(利息分割払い)や保証料不要型が選択肢に入ります。
- 返済期間と完済目標の設定
ローンを何年で返済する計画かを明確にします。長期返済前提なら融資手数料型や外枠方式が有利になりやすく、短期完済予定なら外枠方式一択です。繰上返済を積極的に行う予定なら戻し保証料の恩恵が大きくなるため外枠方式が向いています。
- 各方式のシミュレーション
希望額・期間に応じて、外枠方式の場合の保証料額、内枠方式の場合の金利上乗せ総額、融資手数料型の場合の手数料額をそれぞれ概算します。数字を出して比較することで、総額が一番少ない方式や許容できる負担感の方式が見えてきます。
- 金融機関の比較検討
複数の銀行やネット銀行で金利・保証料率・手数料率の見積もりを取り、総支払額を比較します。このとき団信特約の有無も合わせて考慮し、トータルコストで判断します。自分の属性で優遇が受けられる銀行があれば優先的に検討しましょう。
- 連帯保証人の有無確認
収入合算や共有名義予定なら、誰が連帯保証人になるかを確認します。保証人を立てることで借入額増額などメリットがあるか、自分達がそのリスクを許容できるかを話し合います。可能なら保証人なしで済むプランを選ぶ方が安心です。
- 繰上返済・借換え戦略を用意
将来の繰上返済予定や金利動向による借換え可能性も考慮します。繰上返済を活用するなら外枠方式で保証料返戻を狙う、借換えで手数料型に移行しても良いように今は保証料型にしておく等、ライフプランに沿った戦略を立てます。
- 最終決定
上記を踏まえ、自分たちにとって総合的にメリットの大きい方式と金融機関を選びます。決定したら契約時に方式の選択を間違えないよう申込書類を確認しましょう。あとは計画に沿って返済あるのみです。
以上のチェックリストを活用し、ぜひあなたにピッタリの保証料プランを見つけてください。住宅ローンは長い付き合いになりますが、適切な保証方式の選択は将来の安心と節約につながります。本記事の内容を参考に、賢く計画を立てて理想のマイホーム購入を実現しましょう。安心できるローン契約で、新生活のスタートを気持ち良く切れることを願っています。
松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯 慶智からの提案
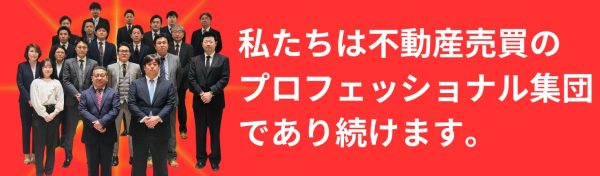
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。住宅ローン保証料の種類と節約術を押さえれば、「どのくらい借りるか」だけでなく「どう返すか」まで見通せる――本記事でお伝えした要点は、まさにそこに尽きます。外枠・内枠・手数料型の比較や繰上返済のメリットを理解した今、資金計画の次のステップは“物件選び”と“売却戦略”の具体化です。ここから先は、非公開情報を含む豊富なデータを活用しながら、ご家族の未来図に最適な選択肢を一緒に描いていきましょう。以下の文章では〈会員登録〉で閲覧できる厳選物件と、〈かんたん自動査定〉による最新相場活用術をご紹介しますので、ぜひお役立てください。
購入をご検討の方へ:非公開物件へのアクセス
不動産購入をご検討の方は、ぜひ当社の会員登録をご利用ください。会員登録を行うことで、非公開物件や最新の市場情報にアクセスが可能です。現在、会員限定で約1000件以上の非公開物件情報をご提供しており、日々新しい情報が追加されています。さらに、ご来店いただければ、経験豊富なスタッフが直接お話を伺い、お客様のご要望に合った最適な物件をご提案いたします。
- 会員登録でできること
非公開物件の閲覧
最新の市場動向に基づく優良物件情報の受け取り
- 次のステップ:来店予約
来店予約をしていただくことで、より詳細なアドバイスと物件選びのサポートが受けられます。
売却をお考えの方へ:簡単査定と戦略的サポート
不動産売却をお考えの方には、簡単で迅速な査定ツールをご用意しております。かんたん自動査定を利用して、お手軽に売却価格を確認いただけます。また、詳細なご相談を希望される場合は、売却査定相談をご利用ください。当社では、最新の市場動向と実績に基づき、適切な査定と戦略的なサポートを提供し、最良の条件での売却をお手伝いいたします。
売却相談の流れ
松屋不動産販売の安心と信頼
私たち松屋不動産販売株式会社は、お客様の安心と満足を第一に考えたサービスを提供しております。たとえば、当社が行った調査では、90%以上のお客様が「初めての不動産取引でも安心して進められた」と高い評価を寄せてくださいました。また、地域密着型の取り組みを重視し、愛知県と静岡県西部における信頼されるパートナーとしての地位を築いております。
実績
- 過去5年間で累計1500件以上の成功事例
- 地域密着型のきめ細やかなサービス
不動産取引の第一歩を、ぜひ私たちと一緒に踏み出してください。皆さまのお問い合わせを心よりお待ちしております。
代表取締役 佐伯 慶智
